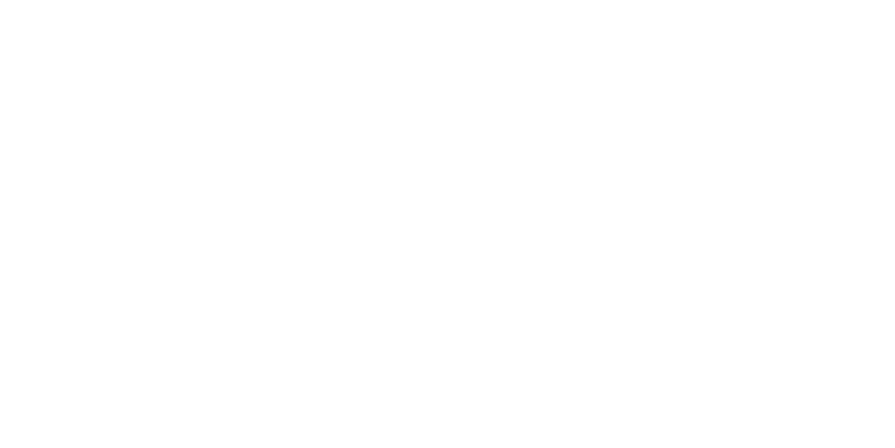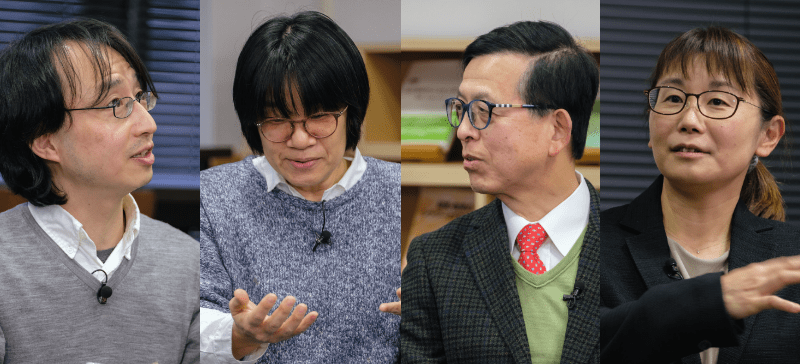文系、理系と分野は異なりますが、幾多の失敗、研究対象への敬意、真摯な学問的態度など多くの共通点があることがうかがえた今回の座談会。先生たちが異口同音におっしゃったのは、「今だったら楽しく学べる」、「いろいろなことを楽しむために必要な知的基盤」という「教養」の重要性でした。これからさまざまな学びを深めていく学生さんへのメッセージと捉えていただけたら幸いです。(山内)
動植物を描いた古い時代の美術作品、
バイオロジーのバックグラウンドなしに、
非常に精緻に描写できていることが不思議でした。(倉永)
山内:尾崎先生、市川先生、倉永先生には、お互いの動画を見ていただいたうえで、本日、お集まりいただきました。どんな感想をお持ちになったでしょうか。
倉永:市川先生と私とは、分野としては物理学と生物学とでまったく違いますし、私自身は物理学がとにかく苦手で、高校のときから赤点ばかりだったのですが(笑)、研究に打ち込む姿勢は、似たものがあると感じました。尾崎先生とは文系と理系、表と裏というほどの違いがあると思うのですが、先生がおっしゃっていた”絵画の解釈は一つではない、芸術の解釈に正解はない”という点にとても感銘を受けました。自分自身もサイエンスに対しては既成概念にとらわれ ず、先入観を捨てて柔軟に見つめていこうと努力しているので、分野は違えど共通するものがあると感じました。
市川先生にお伺いします、物理の立場から生き物という存在はどのように見えるのか、とても興味があるのですが。
市川:領域によって異なるとは思うのですが、私の場合は、素粒子の塊に見えますね。例えば今、座っている椅子はカタチあるものですが、私からするとほとんど空で、その中に素粒子があって、相互作用があって固まってできたというイメージです。生物も同様で、大本は素粒子によって構成されていて、そこに相互作用が働いて、結果として複雑極まりない存在になる。それはすごいなというのが、生物に対していつも思うところです。(素粒子は)単なる物質だと捉えると味気ないというふうに思えなくもないですが、単なる物質があらゆるものの源なのですね。中でも生命の創発は素晴らしい営みだと思います。


山内:ありがとうございます。続いて倉永先生から尾崎先生への質問を。絵画解釈やものの見方というのが面白いというお話でしたね。
倉永:美術や芸術の題材には、生命や人間、それを創造した偉大な存在が多く現れると思うのですが、バイオロジー(生命学)のバックグラウンドなしに、とても精緻に描写できています。それはどうしてなんだろうとずっと疑問に思っていました。
尾崎:なかなか鋭い質問で、非常に難しい。分野が近いと、本質的な問題というのはあまり問うたりしませんね。何がリアリズムなのか、またわれわれの時代から遠い世界にあるものが、なぜあれほどリアルに描けるのかということは、普段、あまり議論の俎上に載りません。一つは世界観の問題と深く関わっていると私は考えています。ごく簡単にいえば、もの(対象)は存在しているのか、あるいは単なる観念なのか(いずれは消え去る)ということです。モチーフとなる対象をどう考えるかによって、描き方は分かれてきます。
技術的なことを言えば、1万年前には非常に細密で高い精度を誇る作品が登場します。動植物を細密に描き出すテクニックとしては、かなり古い時代に確立されているのですね。現在であれば、計測したり、数値化したりというアプローチもあると思いますが、逆にイメージ化していくことで、対象の中に深く分け入り、沈思していくというスタンスもあると思います。例えば木、動物、何でもそうですが、叩いたら壊れる、あるいは燃やしたら消えるというのであれば、それは存在していないのではないかという問いも立てられます。ならば微に入り細を穿いて描いて何の意味があるのだという向きもありますよね。いや、表現されたものは一つの記号であり、それを包括する全体性があるという意見もあります。その時に実存するモノに向かっていくのか、それともモノを支えている観念を捉えていくのか、という非常に興味深い表現論があります。
17世紀に合理主義哲学の祖であるデカルト(1596年-1650年、フランス生まれの哲学者、数学者。近世哲学の祖)が登場するまでの科学、学問といえば、スコラ学であればアリストテレス(前384年-前322年、古代ギリシアの哲学者)の著作を一生懸命読んでいく、あるいは医学部といっても解剖しませんから、ガレノス(129年頃 - 200年頃、ローマ帝国時代のギリシャの医学者)が著したものを読んで理解するのだ、と考えられてきました。ところがデカルトは『方法序説』(1637年)の中で、実験や観察によって、物事(真理)を極めていくのだと諭しています。方法が違うのですね。デカルトはそれまでの方法論をドラスティックに変えて、新しいものを生み出そうとしました。では、デカルト以前の学者や思想家たちは劣っていたのか、考えが浅かったのかというと、まったくそうではなくてアプローチが違っていたということだと思います。


山内:モノと観念という関係は、とても面白いですね。例えば素粒子は、実際は肉眼では見えないわけですよね。理論上、観念として観察するのか、それとも実際にモノがあるからそういう観念が出てくるのか、科学的な営みとしてはどうなのでしょうか。
市川:モノというか、観察事実があるから、観念が出てくるんだと思います。モノがあるからということ自体が、私には理解できない言葉になっていて、モノがあるというのは要するに観察しているわけですよね。手で触れる形であるというのは、現実には電磁気の力で触っているわけです。それと検出器を使って素粒子が通ったことを確認するのと何の違いがあるのかというと、特に違いはないのです、少なくとも私の中では。
山内:例えば、クォークよりさらに小さい存在があるんじゃないか等、予言ができるときがありますよね。それは観察できていない状態にもかかわらず「あるのではないか」と思われているのですか。
市川:その観察っていうのは、どこまでいっても間接的なんですよね。みなさんは手で触れることができたら、「ある」と思うかもしれませんが、それだって言ってみれば電気の力で感じているだけなのです。クォーク自体に直接触れられないと思うかもしれませんが、クォークが存在することで発生するような現象が起きているというのが間接的に観測されたら、それはあるというように解釈するのが私たちの科学的態度です。素粒子物理学を懸命に勉強してきた身からすると、触れられれば「ある」と思うほうが幻のようなものに思えます。


サイエンスのフィールドで、自然科学が指してる客観性と、
人文系がいう客観性はまったく異なる。
決して優劣ではなく、違いがあるということだと私は考えています。(尾崎)
山内:続いて、尾崎先生のほうから市川先生、倉永先生の動画を観て、感じたことをお話しいただけますか。
尾崎:敬称は先生ではなく「さん」でよいですか。倉永さんや市川さんのお話を伺って、「ものすごく共通してるんだな」と思いました。一つは、みんな失敗を経てきているということ。でも、それに負けない、ポジティブなのですね。それから倉永さんが、小さい頃から偉人伝を読まれてきたということでしたけど、僕も浪人時代に吉川英治(1892年-1962年)の『宮本武蔵』を耽読していまして、人間とはどういうふうに生きていくのか、ということを懸命に考えていました。実は『宮本武蔵』は創作箇所が多く、吉川英治が考える理想的な人間像をつくっていったのだと理解していますが、自分とは違う人に憧れる、あるいはそういうものに触発されるというのは、理系・文系にかかわらずあるのだなと思いました。
市川さんのビデオでとても面白かったのは、アインシュタイン(アルベルト・アインシュタイン、1879年-1955年、理論物理学者)の時間のお話ですね。時間が伸び縮みするというのは、感覚的にはわかりにくいのですが、興味をそそられました。
山内:ありがとうございます。尾崎先生の研究では、作品(研究対象)を見る主体(自分)というものがどうしても入り込んでくると思います。そのような主観のようなものは、排除しようという方向なのか、むしろ重視しようという方針なのでしょうか。
尾崎:難しいですね。科学、サイエンスといったときに、自然科学が指してる客観性と、人文系がいう客観性はまったく違うものだと思うのですね。私たちが向き合う歴史的な事象というのはすでに終わったものであり、今では凍り付いてるものです。それを氷解させるように読み解きながら、イマジネーションを働かせ、クリエイティブに動かしていきます。もう一度そこに空間と時間をにじみ出させるという作業をするわけです。ですから非常にシンプルな分け方ですけど、自然科学、そして人文系のそれぞれが目指しているものは、決して優劣ではなく、違いがあるということ。私はそのように考えています。
かつて日本には遥かなるヨーロッパへの憧憬が強くありました。例えばテーブルウェアなどは王侯貴族が使っていたブランドなどが人気を博しました。もちろん今でも多くの日本人に愛されています。その逆のことが16世紀、17世紀に起きていました。中国の陶磁器である白磁・青磁・青花などの豪華な器や、日本の伊万里焼(17世紀半ばからオランダ東インド会社によって欧州に輸出されていた)が、ヨーロッパの人々を魅了しました。
「白」という色は、清らかで好感が持てる、ポジティブな印象がありますね。それはヨーロッパにおいても同様です。しかし16世紀の宗教改革以前、白は墓碑の色であり、不吉な意味合いを帯びていました。ところが16世紀の半ば、壁を真っ白に塗った教会がチューリッヒに現れました。それを見たカトリックの司祭は「何て不吉なんだ」という言葉を残したのですが、プロテスタントの聖職者は「素晴らしい、美しい」と褒めたたえた。まるきり違う反応です。つまりプロテスタントは白くすることによってカトリックの美意識をつぶして、自分たちの優位性を保とうとしたのです。
さきほど言った陶磁器には青と白があるのですが、基本的に地の色は白なんです。しかしヨーロッパの研究者は、青と白を組み合わせて考えるのですね。そして「ブルーだ」と言うのです。ブルーの力が強いというわけですね。だけど私は、白のほうが際立って見えます。つまり影響というのは、外からだけではないのです。自分の内発的なものがあって初めて外部を受け入れられるんですよね。コノテーション(内包)とデノテーション(外示)、二つ重ならないと影響というのは表出されないのですね。


市川:ひとつ質問いいですか。尾崎先生が「いろいろな失敗してきたという共通項がある」とおっしゃっていましたが、美術史などの研究ではどういう場合が失敗なのですか。
尾崎:一つは研究対象・テーマの選択を間違えるということですかね。私の場合は、17世紀のオランダ美術をテーマにしましたが、別にオランダ美術だけに関心を抱いたわけではなくて、イタリアや中世など、面白そうだなと感じるものがありました。ですから学生の皆さんには、純粋に興味が持てる対象に取り組んでほしいと思っています。次に、研究でいえば、仮説を立てたけど、実証、つまりデータが出てこないということがありますね。説得するための材料が足りないので、少し寝かせておいて、ある程度、時間を経てから見直してみると…やはりこれは無理筋だったのだとわかります。それでも諦めきれずに手を替え品を替えで、何かできるんじゃないかなと思っても物にはならない。どこかで断念せざるを得ないということですね。こういう結末は結構あります。そうかと思うと、パッとした思い付きで関係性を見いだせて、首尾よくいくこともあります、稀ですけれど(笑)。ですから論文を執筆するときは、常にハラハラしていますね。ハラハラの中に、僥倖に巡り合ったかのような研究の果実があって…そういうところは研究者冥利と言い換えてよいのかもしれません。
山内:改めて市川先生から映像のご感想をお願いします。
市川:私は、ビデオでメッセージとか聞くのはすごく苦手で、実はほとんど頭に入ってきませんでした(笑)。倉永先生が映像の中で、客観的に自分を見過ぎてはいけないとか言っておられて、私だと考えもしないようなことですけれど、すごいなと思いました。尾崎先生のお話は最初、よくわからなかったというか、感性がまったく違うな、違う世界の人だなと感じました。それで今日、直接伺っても、はじめはやはり観念的で理解が難しかったのですが、中世で白がどういうふうに受け入れられるようになってきたかという話以降、私の頭の中に入ってくるようになり、やっと面白いと思えるようになりました。こんなにも言葉が違うんですね、驚きでした。


教養教育は、ほんのちょっと掘り下げると
絶対、面白いところが隠れていると思う。
卒業から何年も経った今だから言えること。(市川)
山内:新入生は志している分野以外のことも学ぶ機会があると思います。特に教養教育の意味と意義についてお話しいただきたいと思います。
市川:私は本当に理系バカというか、大学生のときに真面目に教養科目に向き合ってこなかったのですね。でも、たくさんの経験を重ねると、ちょっとだけ耳に挟んだだけでは興味が湧かないようなことでも、ほんの少し掘り下げるととても面白いことが隠れていることがわかりました。授業に出なきゃいけないから、取らなきゃいけない単位だから、取りあえずは出席しようというのではもったいないですね。ほんの少しの前向きさや積極性が景色を変えることがあります。これは卒業から何年も経った今だからできるアドバイスです。
尾崎:特に文系の学生さんに言いたいのですが、やはり理系の科目はしっかりやるべきだと思います。中でも量子論の考え方というのは、21世紀に生きる私たちが科学リテラシーとして備えるべき知識だと思います。文系は理系を、理系は文系を、とは非常にありふれた物言いですが、ぜひ努力してやってほしい。きっとどこかで役に立ちます。
倉永:私も様々な経験を積んだ今でしたら、教養の授業も楽しめると思いますが、学生のときは敷居が高かった、というか正直わからなかったですね。ですから教養科目を楽しもうね、というようなことは言えた義理ではないのですけれど(笑)。受け身で臨む授業と、自分から何か知りたい、何かを得ようという態度で向き合う授業とでは、吸収できるものが違ってきますね。また、授業のために教壇に立っている先生の言葉と、自分の研究の話をしている先生の言葉とでは伝わってくるものが違うので、先生の個性やパーソナリティーのようなものを感じながら聞くと、面白いことが見えてくるかもしれません。
例えば、何かピンときたり引っ掛かったりするキーワードが出てきたら、先生に直撃して伺ってみてもいいと思います。すると先生の思索の背景や科学的裏付けなどが解り、共感なり興味なりが新たに生まれることもあるでしょう。それが視野を広げるきっかけになればいいですね。受け身の姿勢ではなく、自ら積極的に能動的に授業に臨むことが、大学で学ぶ最初の一歩になると思います。

飽くなき探究心と挑戦的研究。
まだわからないことがある、と
どんどん突き進んでいく原動力はどこにあるのか。(山内)
山内:今、倉永先生がお話をされた能動的というところに関連しますが、みなさんは常に研究に対する飽くなき向上心、好奇心やワクワクする気持ちを持ち続けておいでだと思います。現在は、インターネット上に多くの情報や集合知があふれていて、少し調べれば知りたいことにアクセスできます。それでもなお、未知の領域に分け入る、突き進んでいく原動力は、どこから生ずるものなのでしょうか。
市川:何というか私の場合は、原動力が必要な理由がわからないほどです。スマートフォンの中にもないし、どこにもない、誰も知らない、何でそうなっているのか、どう考えても不思議だという現象が目の前にあるのですから、知りたいと思うのは当然です。
今はたまたま素粒子物理を専門にしていますが、たとえば生命がどのように誕生したのかをはじめ、ネット上では真理に迫ることのできない謎や難問がたくさんあると思います。
尾崎:ものすごく単純ですけれど、楽しく生きたいという望みがありますね。そして時間とともに時代とともに、自分という存在が少しずつ変わってきているとすれば、「さて、自分とは一体何なんだろう」という関心や疑問が沸きあがってきます。新しい刺激を受けたことによる自分の中の新しい発見、これは本当にわくわくするものなのです。心象を説明する言葉は難しいですが、わくわくする、がしっくりきますね。本日のこの座談会の席も、普段はあまり接点のない異分野の研究者の方と話を交えることができて、わくわくと面白いです。
僕は、エネルギッシュにわくわくして生きてる人を見ると楽しくなります。よき影響を与える…とは受け手側の感受性もあるので容易なことではありませんが、少なくとも空気をよどませない人間になりたいと思っています。
倉永:科学とは、先行研究に敬意を払いつつ、疑うことから始める、批判する態度と勇気が求められるという側面があります。パソコンやスマートフォンで調べた結果というのは、すでに教科書に載っていることだったり、授業で展開される話だったりしますよね。インターネット上に書いてあることに対して、誰の言説なのか、どのような根拠なのか、過去にはどういうことが言われていたのかという背景とエビデンスを考えるだけでも、内容を深く理解する上ではとても役に立つと思います。
私の専門領域は、インターネットで調べるだけではわからないことがたくさんあります。分野以外のことは、ネットで調べて、さらに調べて、さらにネットで調べてと深掘りをして、何となく納得したような腑に落ちたような気になるというのはあって、それはそれで面白いなと思います。そういうことができるのはすごく楽しいですね。



山内:ありがとうございます。最後、何かご質問などがあれば。
市川:質問ではないいのですが、尾崎先生が「楽しむため」という旨のことをおっしゃいましたよね、私も全く同感です。今、勉強や研究するモチベーションというのも、別に自分をもっと高めようとか、世の中の役に立とうとか、そういう大上段から構えたものではなくて、自分が楽しみたい、いろんなことを知ってることによって面白いことが広がっていくというのが、主なモチベーションなのですよね。
大学の勉強を通じて、実践的に役に立つようなことを身に付けるのはもちろん大切なのですが、いかに自分がいろいろなことを楽しめる人間になるかということもありますね。そのために多くのさまざまなことを知っておく、勉強しておくというのが、非常に重要なのではないかと思います。高校までの勉強とは違って、自分が楽しむための勉強という観点があるといいですね。
尾崎:全く同感ですね。自分にとって面白いなと思ったことに遭遇すると、俄然、目が冴えてくるって感じがありますね。だからあんまり難しいこと考えないで、楽しいことをやっていくために生きていこうと、そういう境地です(笑)。
倉永:教えを乞い、導かれるというのは大学の4年間が最後だと考えたほうがいいですね。その時間とチャンスを無駄にしないでほしいという強い願いと助言を、最後のメッセージとして伝えたいと思います。
山内:尾崎先生、市川先生、倉永先生、本日はお忙しいところ、ありがとうございました。