偉人伝を読むうちに「研究者」が自分の将来像のひとつに。
偉人伝を読むうちに「研究者」が
自分の将来像のひとつに。
俗に「三つ子の魂百まで」といいます。科学的なエビデンスは抜きにしても「環境が人をつくる」という側面は否めないと思います。私は、本棚にたくさんの偉人伝、特に理系研究者の伝記が並ぶ家で育ちました。小学生にもなると、どんな夢を持っているか、将来はどんな職業に就きたいかなどを子どもなりに語る機会がありますが、私のなりたいものの一つに研究者が入っていたのは、おそらく古今東西の研究者の物語に触れてきた影響からだと思います。科学読み物である『ファーブル昆虫記』(ジャン・アンリ・ファーブル、1823-1915年)を読んだ時には、アリの生態に強い興味を持ちました。離れた場所にあるエサを探してきて、道標もなしに巣まで戻るという素晴らしい能力。小学生だった私は、巣からエサ場までの間にいろいろな障害物を置いて、飽かずに観察したものでした。
伝記に書かれているのは華々しいことだけではありませんよね。――自分の興味のままに事象を追究していくのだけれど、途中、好奇の目にさらされ、反対や迫害を受け、経済的にもひっ迫する。苦心の末、ついには偉大な発見や創作を成し遂げるのだけれど、活動期にはその功績が認められずに、最晩年や後世になって称えられる――というような筋立てが多いと思います。私はどちらかというと、そうした苦労譚にシビれるほうなのです(笑)。研究者になって、何かを成したり発見したりというよりは、人ではなくモノと向き合って、自分一人で何かをやってみたいと考えていたように思います。
高校生になり進学が視野に入ってくると、理系か文系かを選択をしなければなりませんが、偉人伝を通じて自分が感銘を受けた人たち…ガリレオ・ガリレイ、ファーブル、アルフレッド・ノーベル、マリ・キュリーが理系だったこともあり、自然科学を強く意識するようになりました。でも、どういう分野に進みたいのか、どんなテーマを掲げたいのかというのはまだぼんやりとしていて、授業などを注意深く聞きながら探っていたのですが、バイオマスという生物資源から燃料をつくるという研究分野があると知り、俄然、興味を抱きました。一方で、私は“おばあさん子”だったのですが、その祖母が果樹農業を営んでいて、そのたいへんな働きぶりを目の当たりにしてきました。営農がもっと楽になればいいのに、とは私の祈りにも近い思いでした。バイオマスなどの生物工学か、農業(植物学)か、どちらも選べる理系に進みました。
電撃的出会い、瞬間的決意。「先生のところで研究がしたいです」
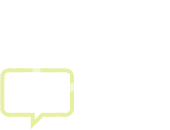

電撃的出会い、瞬間的決意。
「先生のところで研究がしたいです」

大学に入ってから紆余曲折がありました。それはネガティブなものではなく、一期一会に導かれて研究の道が開かれた、自分がいいと思う方向に進んでいった結果、今ある場所につながれたという感じです。私の状況が変わっても、父と母は一貫して「自分がやりたいことがあるのだったらそれをやりなさい」と応援してくれていました。周囲の理解と支援に対しては、とても感謝しています。
興味を持っていたバイオマスは、物理的/熱化学的/生物化学的な変換などを利用して生成物を得るプロセスを構築する研究で、物理の知識が必須でした。私は物理への苦手意識を克服することができず、生物工学系の分野は断念せざるを得ませんでした。試験も得意ではなかったので、人気が高い農芸化学に進むこともかなわず、学部4年生の時に畜産学科の研究室に進みました。配属が終わって間もなく祖母が他界してしまって、植物を研究するというモチベーションや執着がなくなってしまったという背景もあります。
現在のショウジョウバエ研究を始めるきっかけは、大学院修士課程の時に訪れます。電撃的な邂逅でした。修士課程の折、首尾よく研究が進捗し、学会発表をさせてもらう機会をいただきました。会場は大阪大学のホール。するとかつて同じ研究室にいた先輩が「大阪に来るのだったら三浦正幸先生(現:東京大学大学院薬学系研究科教授、専門:発生遺伝学)に会ってみては」と声を掛けてくれました。当時、三浦先生は大阪大学医学系研究科の准教授で、紹介してくれた先輩が同じ研究室に在籍していたのです。勧められるがままご挨拶に伺って、学会発表の内容を話したら「すごいね、いいね」ってお褒めいただいて。先生からもご自身が取り組んでおられるショウジョウバエの研究内容をお聞きしました。話がひと段落すると、先生は私に向かって「倉永さん、修士を修了したらどうするの」と。瞬間的に私の口から出た言葉は「先生のところで研究がしたいです」でした。三浦先生とお会いしたのはその日が初めてです。ショウジョウバエの研究が面白そうだと思った以上に、三浦先生のもとで研究がしたいなと直感的に思ったのです。まさに出会いの妙です。
興味と競争どちらも大事。研究はテーマの設定が肝(きも)になる。
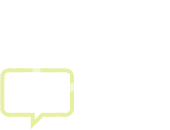

興味と競争どちらも大事。
研究はテーマの設定が肝(きも)になる。

研究とは苦しきことのみ多かりき、というようなイメージを持つ方が多いかもしれませんね。私が考える研究の苦労というのは、出発点の設定です。つまり何に興味がありどういうことを研究するのかということを、数多くの選択肢の中から見つける過程です。研究に取り掛かり始めたら、あとは解明することが目的になり突き進むだけなので、するべきことが明確になります。テーマを選ぶことが一番大変です。目的地としてよい場所なのか、決して到達できない地平なのか、ということですね。
国際的な研究レースという視点からみると、安易に面白そうだと思って飛びつくと、同じような考えで研究を進めている人が世界にはたくさんいて、競争が激しくなります。でも、とてもよく知られる不思議な現象でもいまだに詳らかになっていないというのは、先達が解明の方法に苦労してきたということでもあります。そういう領域はブルーオーシャン(競争相手が少ない、もしくは競争相手がいない未開拓地)の可能性があります。実は、ショウジョウバエの生殖器がサナギの時期にぐるりと回転するという現象も、1900年代初頭には実体顕微鏡レベルでわかっていたのです。どうやって回るのか、回らない昆虫もいるのか、なぜ回らなくちゃいけないのか、どうしてオスだけなのか…という多くの謎があるのですが、それに関する先行研究がないということは、よっぽど面白くないのか、よっぽど難しいのか、どちらかだと踏んで…(笑)。私は面白いと思ったので、チャレンジするほうを選びました。
私はライブイメージング(蛍光顕微鏡などを用いて、生体組織や細胞を生かしたまま、その挙動を可視化し、外部から観察する手法)という技術を使って研究解析を行っているので、「とりあえず見てみよう」からすべてを始めているところがあります。ショウジョウバエの生殖器の回転も1回転するのに12時間以上かかるので、じーっと見ていても全く動く様子がみられません。研究に着手した当初は2時間おきにスナップ写真を撮っていました。それをパラパラ漫画のようにしたら、動いていたという衝撃! 私の好きな言葉に「百聞は一見に如かず」が加わった瞬間でした。
とある研究発表会の場で、初めてショウジョウバエの生殖器が1回転する動画を発表した時の、会場のどよめきは忘れられません。「これだ!」と思いました。もちろん奇抜な動画を撮っただけでは単に「生き物のオモシロ現象」で終わってしまうので、研究テーマとしてはイマイチ(研究するための予算を獲得するのが困難)です。私は、このテーマを一発屋で終わらせるには勿体ない!と思い、さらに詳細な研究を続けました。ちょうどこの時期に、理化学研究所でチームリーダーに採用され、海の物とも山の物ともしれない本研究をサポートしていただきました(本当に感謝に堪えません)。そのおかげで、ライブイメージングの解像度を、細胞レベル、分子レベルまで上昇させて、どんな仕組みで回転しているのかを研究することができました。そしていろいろな方々の共同研究の支えもあって、生殖器が1回転するという奇抜な生命現象を、他の動物やヒトにも応用できる(かもしれない)生命現象の一例(生物モデル)として、世の中に発表することができました。「オモシロ現象」は、「上皮の自己組織化モデル」「上皮細胞集団移動の生体内モデル」へと昇格して、今でも次々と面白い謎を提示してくれます。実は、ハエの生殖器1回転の研究をしているのは、現時点では私たちのチームのほか世界に1グループしか存在しません。しかも少し自慢話になりますが、イメージング動画の美しさは、私たちの研究室がピカイチです。こんなにオリジナリティを出せて、解明すべき謎が満載な面白い研究対象はなかなかないと自負していて、あのとき(もう15年前になります)チャレンジして良かったとつくづく感じています。
多様な分野で経験・見聞を重ねてきたからこそ持ち得た視点。
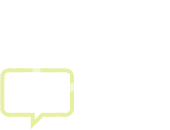

多様な分野で経験・見聞を
重ねてきたからこそ持ち得た視点。

私の学びと研究の道、その出発点(学部)は農学部、修士課程は同じく農学に進み、博士課程では医学系分野に所属しました。そして今、理学系に身を置いています。研究分野のそれぞれが独自の哲学やポリシーを標榜しています。私は、社会還元や社会実装を目指す応用分野から基礎生物学という真理の追究を第一義とする領域に移ってきました。この間、多くの経験や見聞があったからこそ持ち得た視点というものがあります。基礎研究の成果の多くは、すぐさま暮らしや社会で役立てられるという性質のものではありません。しかし、応用分野だけでは解明できない課題が多くあり、根本原理を理解していないと、展開や汎用性が生まれません。知見の太く揺るぎない屋台骨をつくり支えるのが基礎研究です。ですから基礎研究を行っている人は、今やっていることが役に立たないのではないかという杞憂を抱くことなく、この研究こそが大事だという信念を貫くことが必要だと思っています。それは学生さんたちにもわかってほしいと強く願っています。
ひとつの研究テーマに一途に取り組むという姿勢は尊いものですが、研究という営為は自身の関心や興味を原動力とするところがあるので、「これだ!」というものに出会えたならば、新しいことに挑む勇気を持ってほしいとも思っています。私は修士課程のネズミを使った研究から博士課程ではショウジョウバエへとテーマも対象も大きく転換したのですが、環境が変わる不安よりも期待のほうが数倍大きかったです。本当に実験を早く始めたくて仕方がありませんでした。もちろん研究の拠点を移すということは、それまで築き上げてきた人間関係や、勝手知ったる施設、使い慣れた設備などを一旦リセットすることになります。それに対して少しはナーバスになりましたが、「前はこうだった」と以前のホームグラウンドを意識し過ぎず、新しいところで初めから構築する気構えで臨みました。虚心坦懐にイチから学ぶことも大切ですね。
今、ショウジョウバエの研究がとても楽しく、幸いにも成果を挙げていますが、今後はもっといろいろな生き物に目を向けていきたいとも考えています。生命というのは本当に奥が深くて複雑で、全てが謎に包まれていて、到底理解できるとも思えないのですが、とても小さな事象に科学的な説明がつき、そうした理論を全ての生き物を対象に拡張できる可能性がありますから、ワクワクしますね。さらに最近では分子という生き物ではないものが、物質として私たちの生命を支えているということがわかるようになってきて、そこにビビビッときています。生物を考える上の説明、解釈に広げることができるのではないか…私の研究者としての勘や経験知がそう告げています。
私自身は、物理の世界の扉を開けるとは思ってもいなかったのですが、共同研究を通じて、数理モデルといった物理の理論を研究に取り入れる試みを始めています。異なった分野や領域の方々のサポートを得る一方で、私も持てる知識や知見を提供するスタイルにしていけば、win-win(関係する双方が利益となる)でこれまでになかった研究に結実するのではないかと思います。
自分がどうありたいかを掲げ、それに近づく不断の努力を。
自分がどうありたいかを掲げ、
それに近づく不断の努力を。
私は、これまでたくさんの方々の支えをいただき、今この時点まで到達できたという自覚があります。今後は生物学に興味がある若い人たちをサポートする、また進む道を照らすことのできる存在になれたらと思っています。以前は、そんなことを考えたりはしませんでしたが、これからは私の番ですね。それだけ師やメンターとの出会いが貴重なものだったということです。
高校のときは、将来の道や職業の輪郭をたどりながら、大学進学のための勉強をしていく方が多いのではないでしょうか。大学生になると自分の生業(仕事)を見つけるために、どういう知識や技術を身につけなければならないかという、ある程度実践を含めての勉強になっていくと思います。社会への出口を見つけるためには、自身に向き合って客観的に捉えることが重要です。どういう世界でどういう自分になりたいかというビジョンを持てるように意識するということですね。自省も含めてですが、自分だけに集中し過ぎたり、逆に人と比べてばかりだと過小評価/過大評価の闇につながっていく危惧もあります。ですから、卒業/修了後の自分がどういうふうにありたいかを掲げて、それに近づく努力をしていくことがよいのかな、と思います。そして、学生として真摯に学んでほしい、日々を後悔のないように大事に生きて欲しいと願っています。「知之者不如好之者、好之者不如楽之者(これを知る者はこれを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず)」とは、研究に打ち込む私が得心する論語の言葉です。自分の興味のあるものを知識として習得するだけでなく、好きになって欲しい。しかも、その好きを楽しむことができれば、どれだけでも続けられるしチャレンジできるし、最強のパワーになります。学生時代に自分が楽しんで打ち込めるものをぜひ見つけてほしい、そしてそれがライフワークに結ばれていけば素敵ですよね。






