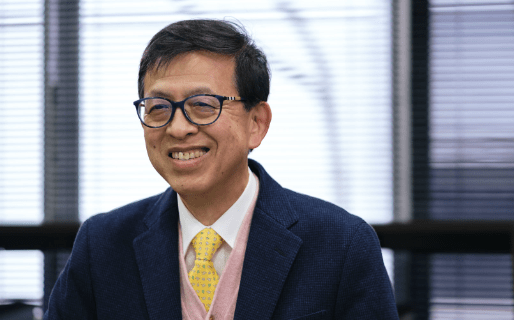法学部志望から文学部へ。曲折を経て、美学と出会う。
法学部志望から文学部へ。
曲折を経て、美学と出会う。
「禍福(かふく)は糾(あざな)える縄の如し」という故事成語があります。私が、福井の高校を卒業してから地縁血縁も全くない仙台にやってきて、東北大学で学ぶことになったのも不運な出来事が起点となりました。これまで私は多くの出会いに恵まれ、奇縁や素晴らしい師・出来事によって導かれてきましたが、「人生、何が起こるかわからない」という感懐あるいは諦念のようなものは、人生の通奏低音になっているような気がします。
元々は文学部志望ではなく、法曹界を目指していた従兄の背中を見て、自分も法学部に進みたいと考えていました。しかし高校3年生の冬、もう受験勉強もラストスパートという時期でしたが、体育の授業(柔道)で骨折をして、入院を余儀なくされたのです。これには困りました。進路について思い悩んでいたところ、病院にやってきた父が「文学部(という選択)もあるよね」と言い出し、なるほど文学部かと思い至りました。友人のお兄さんが東北大学に行っており、「仙台はすごくいいところだよ」という話を耳にし、記憶に残っていたのですね。突然、東北大学の文学部に行ってみようかという気持ちになって、一浪ののち仙台の地にやってきました。
入学後は、何を学ぶのかという選択が待っていました。歴史、哲学、社会学…と興味は尽きませんでしたが、私は「人間はどのように生きるべきか」「自分とは一体何なんだろうか」ということに強い関心をもっており、その問いの答えがある場所は、哲学科なのではないかと考えたのです。しかし、志望動機などを話してみると、「今、哲学はそういうことをするところじゃないよ」と諭されました。
ここで、私にとっては全く未知の学問領域「美学」との出会いがあります。学部2年生の時に受講した美学演習は、カンディンスキー、パウル・クレーといったドイツの近代美術がご専門の西田秀穂先生(西洋美術史学者、1922年-2019年)が担当されていました。先生は非常に豪胆かつドイツ語にもご堪能で、そのパーソナリティと知性に惹かれ、美学というものに興味を抱きました。また、ミケランジェロ、レオナルド・ダ・ヴィンチの研究で著名な田中英道先生(日本の美術史家、歴史家、1942年~)もおられました。先生は、芸術家が残した文字情報(日記、手記、手紙)を介して分析するという研究手法ではなく、純粋に芸術作品だけを通して作者の生き方、思考、有り様、また作品の創造過程などを浮かび上がらせるという斬新な研究アプローチを試みておられました。私はとても面白いなと思ったのですが、この段階では、本格的に美学を専攻するまでには至りませんでした。
ヨーロッパにて。造形作品を通じて立ち現れた心揺さぶる問い。
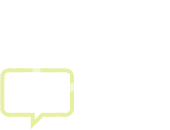
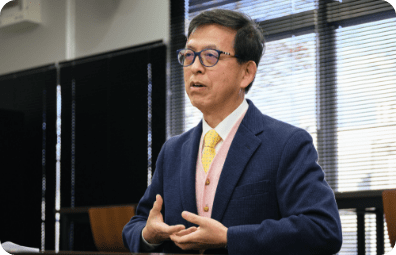
ヨーロッパにて。造形作品を通じて
立ち現れた心揺さぶる問い。
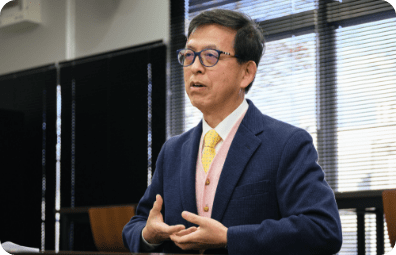
私は文化系の部活動では美術クラブ(当時)に所属していました。ここでは作品を実際に制作するのではなく、美術書などを読んで学んだり、部員たちと議論したりするということが主な活動でした。学部2年生の大学祭の時に(1976年)、運よく高田博厚さん(彫刻家、思想家、文筆家、翻訳家、1900年- 1987年)をお招きすることができました。「美術、芸術を勉強したいのだけれど」と相談したら、「ではフランスへ行って、三つのものを見てらっしゃい」と言われました。ひとつはサント・シャペル(聖なる礼拝堂の意)のステンドグラス、それからクリュニー美術館の『貴婦人と一角獣』のタペストリー、そしてオランジュリー美術館に収蔵されているモネの『睡蓮』。それらを間近にして「何かしら感じるものがあったら、芸術というのが君にとって取り組む価値と意味があることだろう。何も感じなくてもそれは別に悪いことではない、勉強する必要がないということだ」とおっしゃったのですね。私が、アルバイトでためた資金を懐に、アエロフロート(旧ソ連の国営航空会社)の機上の人となったのは、その次の年の春、1977年のことでした。
2か月間ヨーロッパを周遊して、いろいろなことを見聞していく中で、非常に驚かされたことが二つありました。一つは美術館や教会に掲げられる芸術作品には、キリストの磔刑図をはじめとして、血が流れるような凄惨なモチーフが多いということです。どうして教祖が罪人として処刑されなければならなかったのか…。もちろん聖書を読み解けばその背景と経緯が理解できますが、私としては造形作品が強く訴えてくるものから、どうしてもその整合性が見出せなかったのです。例えば、釈迦は80を超えたところで涅槃に入りましたが、彼の死の枕辺には多くの人が集まったといわれています。片や、キリストは磔になって最期を遂げている。どちらの宗教を選びますかと問われたなら、私でしたら一も二もなく釈迦の教えを選択すると思います。にもかかわらず、キリスト教はあまねく伝播し、現在では世界で最も多くの信者を擁する宗教となっている。ここにヨーロッパの一つの秘密があるのではないかと感じたのです。
もう一つはなぜあれほどまでに裸体図が多いのかということ。視覚的なものからくるインパクトというのはとても大きく、文字資料が教えてくれるものとはちょっと違うのではないかと強く感じました。ヨーロッパとは一体何か。自分たちとは非常に違ってるものは一体何なんだろうかということに惹きつけられたわけです。それまで本格的に美術を勉強してこなかったため、固定概念や先入観にとらわれることなく、鑑賞し、思考できたことも大いに幸いしました。ヨーロッパとは一体何なのか。そこを出発点として、美術というものに向き合っていけるのではないかと考えたのです。数多くの出会いと縁に結ばれて、少しずつ学問の道が定まっていきました。
普遍的、理想的な人間理性の概念「真・善・美」を礎石に。
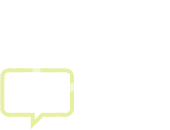
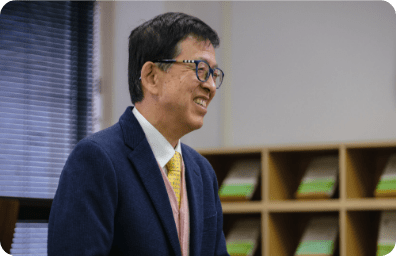
普遍的、理想的な人間理性の概念
「真・善・美」を礎石に。
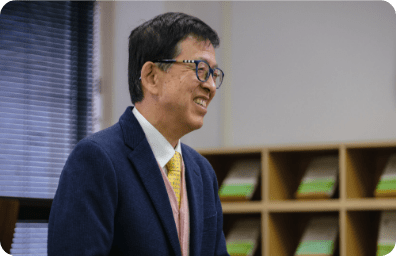
私が所属していた研究室では、一人の特定の芸術家を定め、その人物が手掛けた一つの作品をテーマにするという研究手法がとられていました。私が触発された作品に、ローマのボルゲーゼ美術館所蔵のカラヴァジョ(1571年-1610年)『ゴリアテの首を持つダヴィデ』があります。当時は、なんてすごい画家がいるんだろうとただただ感嘆したものです。カラヴァジョにはホモセクシャリティの傾向があったといわれています。つまりアンビバレントな、二律背反的なものを抱え込んでいます。正邪相携えているような、異なった二つの価値というものを一つの中に包含しているところに、私は魅せられていたのではないかということは、後から自分の中で言語化し再構築できたことです。カラヴァジョは研究テーマとして選択しませんでしたが、自身の気づきと論理を架橋する思考法に覚醒したきっかけとなりました。
高校時代は、答えがあることを覚えていく、あるいは答えを人より早く導き出せるという学びに重きが置かされていると思います。しかし、大学以降はアウトプットしていく、つまり何かを生産し、表現していくことが求められます。そのためにはマインドセットの転換が不可欠です。自身が無意識に当たり前だと思っていることをまず疑ってみること。それから世の中で良い/好ましいと思われていることが、本当にそうなのだろうかと疑問を持つということです。例えばセキュリティという概念・システムがあります。通常、「セキュリティは悪」という人はいないと思います。しかし、セキュリティを厳重、厳格に突き詰めていくと、甚だ不自由な状態を招来することになりかねません。つまり良いと思われることを厳しく追求していくと、場合によっては悪くなるのだということ。こうした逆説に着目していく必要があります。
また、大学に入って、意気軒高、早く専門的なものを勉強したいと思われるかもしれません。私は、学問・研究の根底に「真・善・美」の三つを据えなさいと言っています。これはプラトン(古代ギリシャの哲学者、紀元前427年-紀元前347年)を源流とし、イマヌエル・カント(ドイツの哲学者、1724年-1804年)が唱えた普遍的かつ理想的な人間理性の概念です。「真」は、哲学に限定するのではなく、科学、社会分野における今日的な課題も視野に入れなければならないでしょう。「善」は、人間は何を為したらよいのか、その行いにどういう意味があるのかと問うことです。つまり自分で判断する力がとても重要になります。それから「美」。美しいとは必ずしも芸術や美術だけではなくて、価値、所作、行為などもあります。調和も必須の要素です。これら「真・善・美」をトータルで考えて、自分が生きている時代、現代において何が問題になっているのだろうかという視点を持つことです。エルンスト・ゴンブリッチ(オーストリア系ユダヤ人の美術史家、1909年-2001年)は、“学問には分野があるのではなく、問題があるだけだ”と述べています。問題意識を持つことによって、自分が抱える問題を解決する、あるいは解決に向けて深めていくように学びなさいということですね。学問・研究とは“分野”に拘泥し、深耕させていくことばかりではないと思います。
芸術の探究には、今を生きる者たちの心象風景が織り込まれる。
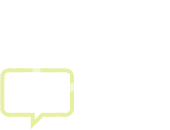

芸術の探究には、今を生きる者たちの
心象風景が織り込まれる。

ベネデット・クローチェ(イタリアの哲学者・歴史学者、1866年-1952年)は、“すべての歴史は「現代史」である”と喝破しています。歴史というものを説明していくときに、通常はわかりやすさのために通時的に年代順に説明していきます。しかし、芸術作品はギリシャ時代の作品も、レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452年-1519年)も、ミケランジェロ(1475年-1564年)、パブロ・ピカソ(1881年-1973年)、アンディ・ウォーホル(1928年-1987年)のアートも同じ空間に置くことができます。つまりの共時的に、同時代的に全部捉えることができます。それを現代に生きている鑑賞者が、現代の問題意識に照らしてみるわけです。鑑賞態度あるいは評価には、現代人の心象風景が織り込まれます。ですから芸術と向き合う者は、つねに現代という時代をどう捉えるのかという問いと対峙しなければなりません。
可能なのか否か、自分の中でもまだ錬磨できていないのですが、研究という営為を通じて、自分とは何か、あるいは社会とは何かという問題に関わっていくことはできないかと考えています。最初のステップは、一つの作品から促されてくるものを論点として掲げ、それにどのようにアプローチしていけばよいのかを考察することから始まります。たとえ先達にどんなに優れた研究者がいたとしても、生きてる時代、場所が違い、観念、感覚、センスなどすべてが異なります。100人いれば百様の価値がある。研究が一個人から立ち上がる営為である限り、終わりはないのです。
きわめて個人的な思索であっても、現代の課題という俎上に乗せて発信することができます。それは研究者にとっての大きな果実であり、醍醐味です。わかったと膝を打った時の、あのワクワクした感懐は何物にも代えがたいものがあります。そこに至るまではとても辛い。学生だから苦しくて、研究者と呼ばれる立場になると楽になるというわけではなく、常に試行錯誤しているという有り様です。しかし、ぱーっと目の前が開けた時の感動、僥倖を求めて私たち研究者は飽くなき挑戦を続けているともいえるのです。
世界を見晴るかし、学問・研究の新しい地平の、その先へ。
世界を見晴るかし、学問・研究の
新しい地平の、その先へ。
若い時代というのは、勢いと突破力がありますが、経験知の蓄積がなく、周囲の壁が高く見えるものです。歳を重ねれば、裏道や迂回路も見えて、そう焦らなくても大丈夫という鷹揚な気持ちになるものですが、若い時というのは正面突破を試していかないと気が済まない、性急に結論が欲しくなるという傾向があるでしょう。これは私も経験済みです(笑)。ですから少し障害があると早く別の道に行った方がよいのではないかと焦ったりしますが、ここは勇気をもって困難と思える道に一歩踏み出してほしい、チャレンジしてほしいと思っています。失敗したとしても、それが終わりではありません。人は何度でも立ち上がれます。リターンマッチが待っています。つまずきから次のステップに向けた糧を得ることだってできます。壁の先に、何か面白いことが待っていると思えれば、学問・研究もこれまでとは違った風景として立ち現れてくるのではないでしょうか。
私の好きな言葉にネルソン・マンデラ(南アフリカ共和国の政治家、1918年-2013年)の「It always seems impossible until it’s done.」があります。何事も達成するまでは不可能に思えるものです。学生のみなさんにはぜひ挑戦的研究の扉を開き、学問の新しい地平を切り拓いてもらいたいと願っています。志を高く掲げ、いにしえの鬼才・賢人と語り合い、世界を見晴るかして。