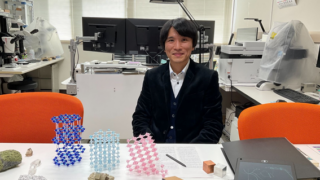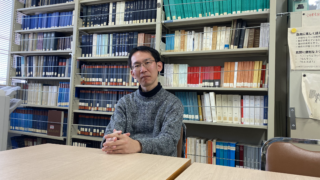<撮影:片山>
関根 久子(せきね ひさこ)先生
東北大学 大学院農学研究科 教授
研究キーワード:線形計画法 環境会計 国際比較 農業経営
——————————————————————-
記事作成:2025年1月
メンバー:辻勇吹樹(理B4)、片山歩紀(理B4)[New Blows]
研究内容
小麦やじゃがいもは、私たち消費者にとって身近な作物である。しかし日本における自給率は、小麦は18%、じゃがいもは68%と低い状況にある(令和5年度)。日本の面積当たりの収穫量(単収)は西欧諸国と比べて伸びが小さい。日本国内だけを見ていると規則や制度は前提条件となり問題点を見つけるのが難しい。国内だけでなく、海外の農家や農業機関などへの聞き取りを通して、社会科学的な視点から単収向上を実現する方策を検討する。
関根先生は、2023年度まで農研機構という研究所に所属されていたが、2024年度から東北大学に所属し、教鞭をとっている。
目次
|
Q1. 過去の悩みとその解決方法
——————————————————————————–
“「若い人が挑戦したいならやればいい」と言ってくれました”
農業経済学について
農業経済学で扱うデータは、統計処理で得られたもの、アンケート調査で得られたものなどがあります。その中で「オリジナルのデータを現場で取ってきて解析する」のが、私の研究室のやり方です。特に現場で話を聞くところが重要な部分になります。私は、学生の頃から人見知りしない性格ということもあり、現場で話を聞くことを、長年続けています。現場の人にうまく研究を理解してもらえば、調査はスムーズにいきます。本当に小さなツテ、ネットワークを使って調査地に入ります。現場へも1回だけではなく、「また来たの」と言われるぐらい行きます。1回目では、表面的なことしか聞けません。最初に「いくら儲かりますか。」と聞いても、教えてもらえないです。自分は、本気で現場の問題に取り組みたいということをわかってもらうために、何度も行って、関係を形成していきます。
在外研究について
農研機構では「在外研究制度」という若手研究員を対象に1年間希望する国で研究できる制度があります。年に2回、応募のチャンスがありますが、1回に数人しか選ばれない狭き門です。農研機構には2千人近くの研究者がいて、農業経済学分野だけでなく、作物や育種、農業機械など、様々な分野の人たちも応募します。この制度へは、任期付研究員は応募できません。私は、農研機構採用後、5年間、任期付研究員でしたので、応募ができるようになるのを待っていました。5年間の任期が終わるとすぐに「在外研究したい」と上司に申し出ました。周りは、任期付研究員から任期のないパーマネントの研究員になったばかりで「何を言っているのだ?」という反応でしたが、その上司だけは「若い人が挑戦したいならやればいい」と言ってくれました。この時の上司には、その後も申請書作成等で援助してもらい、なんとか狭き門をくぐり、在外研究できることになりました。
ドイツでの研究について
2012年10月から、ドイツにおける小麦の土地生産性が高い理由を明らかにするために1年間ドイツに行きました。まずは、農家調査をする準備をしました。農村調査には車が必要と考え、免許証を日本のものからドイツのものへと書き換えました。ドイツで所属した研究所(Thünen Insitutute)では、自家用車を使って出張できるということで、すぐに自分の車を買いました。現地調査は誰かに連れて行ってもらおうとすると、なかなか行けません。自分で行けるように準備をすれば、農家と直接連絡してすぐ行けます。ドイツ語ができない私が、突如、車通勤したので、研究所の同僚たちも驚いていました。
次は、農家を紹介してもらわないといけません。研究所の人に英語が話せ、小麦を作っている農家を紹介してもらいました。これらの農家には、日本で研究していた時と同じように、何度も通って調査させてもらいました。
ただ、ドイツの小麦単収の高さの理由は半年経っても、分かりませんでした。ある日、研究所の同僚に、日本では品種はなかなか変わらないと話をしたら、ドイツでは品種はすぐに変わると言われました。調べてみると、取引体制が日本と異なり、生産者の品種交替を促進する制度であることがわかりました。日本の取引体制を普通のことと思っていたので、ドイツの取引体制も似たようなものだろうとそれまで思っていました。この違いに気づいてからは、研究は順調に進んでいきました。ドイツでの研究成果はこちらの本にまとめています。
小麦生産性格差の要因分析 : 日本と小麦主産国の比較から | NDLサーチ | 国立国会図書館
Q2. 現在の悩みについて
——————————————————————————–
“問題を持ってくる学生はすごく優秀です”
この4月から東北大学に勤務して、まだ半年しか先生をしていないので、新人です(取材時)。学生の悩みにどこまで寄り添えるのか、私のアドバイスは本当に役に立っているのか、私のアドバイスはかえって学生の悩みを深めているのではないか、と日々悩んでいます。
今のところ、研究室に所属する学生は、検討会の時に自分が分からない部分を明らかにし、問題を持ってきてくれます。問題を持ってくる学生はすごく優秀です。何が問題かわからないというのが一番の問題です。例えば、数学でもただ「難しい」といわれただけでは教えることができませんが、具体的な問題を持ってきてもらえれば、教えようがあります。
教育はすごく楽しいです。学生が自ら選ぶテーマは、私自身の勉強にもなります。一方、教育は怖いです。私の一言で、学生を傷つけてしまうこともあるかもしれない。先生と学生は、上下関係がはっきりしています。教育は楽しいけど、怖いというのが今の悩みです。
違う分野の人と話すことで悩みが解決されます。
過去に一番悩んだのは、博士課程後期1年のときです。苦しい時に救ってくれたのは、工学研究科の研究員でした。彼女は当時後期課程3年で、後期課程1年だった私から見たら、研究も順調で、就職先も決まっていて、すごく順調な研究者に見えました。私の悩みを彼女に話すと、彼女自身も博士課程後期1年の時に、研究について悩んでいたということを知りました。こんなに優秀な人でも悩むのであれば、私が悩むのも当たり前だと思い、救われました。研究は一人でオリジナリティーを追求していきます。自分のテーマを追求するあまり、そこから逃げ出したくなったり、キーワードを見るのでさえ嫌になったりすることもあります。でも、分野が違う人や諸先輩方と話すと、切り替え方とか悩みを脱出するヒントが得られることがあります。
これからは、研究だけでなく、教育に関する悩みもそうして解決していくと思います。
Q3. 学生のうちにやっておくべきこと
——————————————————————————–
“まずは自分の強みを知ってほしいです”
私は、志高く農業経済学を専攻したわけではありません。福島県出身で、東北の良い大学ということで、東北大学へは憧れがありました。当時の農学部は、後期の2次試験の科目は数学だけでした。私は数学だけが得意で、数学以外の科目に自信がなかったので、農学部を受験しました。また、私はアトピー性皮膚炎を子供のころから患っていて、水仕事ができません。実験をすると手が荒れてしまいます。入学後は、農学部で唯一実験がなかった農業経済学を専攻することにしました。
私は4年生で卒業し、一度、就職しています。5年間働きました。しかし、指示通りにやる仕事に面白さを感じませんでした。自分が面白いと思うことで、お金をもらうにはどうしたらいいのか考え、東北大学の博士課程前期に入学しなおしました。博士課程前期の2年間は、社会人の間、勉強していなかった反動で、勉強が面白かったです。そうして勉強を進めるうちに、農業経済学の面白さに改めて目覚めました。そして、博士課程後期に進学することにしました。お金の工面をどうしようと困っていたら、日本学術振興会特別研究員に採用されることになりました。これで博士課程後期の3年間、研究に集中することができました。しかし、特別研究員に採用されたプレッシャーがありました。特別研究員は、周りに「優秀」と思われますが、自分はそんな実力はないというギャップに悩みました。
| でも、それも実力ではないですか? |
私の場合、研究能力というよりも、いいネットワークを作る能力はあったかもしれません。私は、特別研究員の申請書を面白くするために色々な人に原稿を見てもらいました。 指導教授以外の先生方、工学部の友人で特別研究員に採用になった人にも見てもらいました。そのおかげで、誰が見ても面白い申請書になったと思います。
私は農業経済学の専門家ですが、 志が高く、日本の農業をなんとかしたいとかいうことを幼い頃から思っていたわけではありません。自分が経験したり、他の人と交流したりする中で、農業経済学が面白いと思うようになりました。そして、自分の強みを生かして、研究していると思います。
学生の皆さんにも、まずは自分の強みを知ってほしいです。そして、自分が面白いと思う人生を歩んでもらいたいです。
関根先生、取材させていただきありがとうございました!
「化学」からみた「農業経済学」
インタビュアーの専門分野から、インタビューの内容を受けて共通点や違いを深堀りします。
理学部化学科4年 片山歩紀
農業経済学は、農業という人間活動と経済のつながりを分析する学問です。私は化学を専攻しており、普段は分子や化合物の性質を扱っています。一見、農業経済学とは遠く離れた分野に感じられるかもしれません。しかし、今回のインタビューを通じて、農業経済学が農業という産業において「化学」と「消費者」をつなぐ重要な架け橋であることに気づかされました。
農業の土台となる化学
農業は、植物が光合成を通じて地球環境からエネルギーと物質を取り込み、成長する営みの上に成り立っています。この成長過程は、化学反応の連続です。例えば、窒素、リン、カリウム(いわゆる三大栄養素)は植物の成長を支える不可欠な化学要素であり、それらの効率的な利用や、土壌中での化学反応は作物の収量や品質に直接影響を与えます。化学が農業に貢献した最も有名な例として、ハーバー・ボッシュ法があります。この技術は、空気中の窒素を化学肥料の原料として利用可能にし、農業生産性を飛躍的に向上させました。それまで肥料は天然由来に限られ、生産量が制約されていましたが、この方法により窒素肥料の大量生産が可能となり、食糧供給の増加を実現しました。現在、世界人口が増加し続ける中で、食料を十分に供給できている背景には、化学技術の貢献が大きく関わっています。
農業は自然科学でもあり人文科学でもある
化学を専門とする身として、農業の自然科学的な側面にばかり注目してしまいがちです。もし私が農学の研究をするなら、いかに発育の早い品種をつくれるか、いかに高性能な肥料を開発できるか、といったテーマに興味を持つでしょう。もちろん、こうした自然科学的なアプローチも農業の発展には欠かせません。しかし、これだけでは農業は発展しません。農業を行うのは人であり、農業の恩恵を受けるのもまた人です。すなわち、人文科学的な考え方で農業を捉えることが不可欠なのです。
たとえば、新しい品種や肥料を開発したとしても、それが農家にとって高価すぎたり、現場の作業工程に適していなかったりすれば、実際に利用されることはありません。また、地域ごとに異なる気候条件や土壌の特性、さらには文化的背景や慣習が農業の形を大きく左右します。これらの要因を無視して科学技術だけを押し付けても、現場での受容は難しく、ひいては農業全体の発展を妨げる結果になりかねません。
関根先生のインタビューで印象に残ったのは、「農家と何度も直接対話を重ねることで、信頼を築き、課題を引き出していく」という姿勢でした。これはまさに人文科学的な視点で農業を捉える例です。農家が抱える経済的、社会的、文化的な課題を理解し、それを踏まえた技術の開発や政策の提案が重要であることを示しています。農業を持続可能に発展させるには、自然科学と人文科学の両面から農業を考える視点が不可欠です。
化学と人をつなぐ
化学からみた農業経済学を一言で言い表すなら農業経済学は化学と人の架け橋です。農学の専門家として自然科学的にも人文科学的にも深く農学を理解し、化学と人をつなぐ存在です。農業の中で化学の成果を人に伝え、普及させる。逆に人からニーズを聞き出し化学の研究を加速させる。これらをおこなう学問が農業経済学であり、化学と農業経済学は切っても切り離せない関係だといえるでしょう。